わからなさの前に
一緒に座ってみる。
共に考えることから。
[ 哲学者 ]
STORY_04
REI NAGAI
PHILOSOPHER


ライブ会場に美術館、学校から寺社に至るまで。一見「哲学」という言葉からかけ離れた場所に赴き、年齢も性別も肩書きもさまざまなひとたちと対話を重ねる哲学者の永井玲衣さん。たまたま誰かがつぶやいた問いから、哲学はすでに始まっているという永井さんが大切にしているのは「ひとそれぞれ」で終わらせないこと。誰かと共に考え、話し合う場をつくる理由についてお話を伺いました。


――永井さんにとって「哲学」とはどのようなものなのでしょうか。
「哲学」というと専門的で難しい学問のように思われてしまうのですが、本来は極めて身近で日常的な営みのはずなんです。簡単に言うと、問うて考える、その行為自体が哲学で、わたしたちは日々すでに哲学してしまっているはず。それはもやもやしたことや言葉にできない苛立ちや寂しさや悲しみ、そうした形でおそらく表現されているんですけれど、こんなことが哲学なわけがないと思って忘れてしまう。そうしたことにひとつひとつ立ち止まって、これは哲学というもので、一緒に考えてみようよ、と誘うことが「哲学対話」なのかなと思っています。
――そもそも哲学者を志したきっかけはなんだったのでしょう?
世界って、わからないことであふれていますよね。今こうしてお話をしている光景すらも、なぜここでお話をしているのだっけ?という気持ちになりますし、目の前の建物も、ひとが建てたものだとあらためて考えてみると、どうしたらそんなことが可能になったんだ?とか、自分の手はなぜこんな形をしているのだろう?とか。わからなさであふれている世界が、怖かったんですね。そこで答えを探すように文学をたくさん読んでいたら、あるときに出会った哲学の本に「あなたが考えるんだよ」と書かれていて。世界のわからなさの前に立ったときに、この「わたし」がそれを取り扱っていいんだ、とびっくりしました。それはわたしにとって、世界と関係を結び直すようなものだったんですよね。
――そもそも哲学者を志したきっかけはなんだったのでしょう?
世界って、わからないことであふれていますよね。今こうしてお話をしている光景すらも、なぜここでお話をしているのだっけ?という気持ちになりますし、目の前の建物も、ひとが建てたものだとあらためて考えてみると、どうしたらそんなことが可能になったんだ?とか、自分の手はなぜこんな形をしているのだろう?とか。わからなさであふれている世界が、怖かったんですね。そこで答えを探すように文学をたくさん読んでいたら、あるときに出会った哲学の本に「あなたが考えるんだよ」と書かれていて。世界のわからなさの前に立ったときに、この「わたし」がそれを取り扱っていいんだ、とびっくりしました。それはわたしにとって、世界と関係を結び直すようなものだったんですよね。
――永井さんにとって「哲学」とはどのようなものなのでしょうか。
「哲学」というと専門的で難しい学問のように思われてしまうのですが、本来は極めて身近で日常的な営みのはずなんです。簡単に言うと、問うて考える、その行為自体が哲学で、わたしたちは日々すでに哲学してしまっているはず。それはもやもやしたことや言葉にできない苛立ちや寂しさや悲しみ、そうした形でおそらく表現されているんですけれど、こんなことが哲学なわけがないと思って忘れてしまう。そうしたことにひとつひとつ立ち止まって、これは哲学というもので、一緒に考えてみようよ、と誘うことが「哲学対話」なのかなと思っています。
――そもそも哲学者を志したきっかけはなんだったのでしょう?
世界って、わからないことであふれていますよね。今こうしてお話をしている光景すらも、なぜここでお話をしているのだっけ?という気持ちになりますし、目の前の建物も、ひとが建てたものだとあらためて考えてみると、どうしたらそんなことが可能になったんだ?とか、自分の手はなぜこんな形をしているのだろう?とか。わからなさであふれている世界が、怖かったんですね。そこで答えを探すように文学をたくさん読んでいたら、あるときに出会った哲学の本に「あなたが考えるんだよ」と書かれていて。世界のわからなさの前に立ったときに、この「わたし」がそれを取り扱っていいんだ、とびっくりしました。それはわたしにとって、世界と関係を結び直すようなものだったんですよね。


――「対話」という言葉は「議論」とも異なります。「対話」とはなんなのでしょうか?
議論は他者を競争相手とみなしますが、世界はあまりにわからないことだらけなので、協力し合わないとどうにもならないと思うんです。ひとは誰しも生まれたけれどいつかは死ぬことになっていて、死んだ後はどうなるかも、なぜ生まれてきたのかもわからない。そうした共通するわからなさのなかに生きているからこそ、一緒に笑ってしまって、探求しようと協力し合えるはず。この「わたし」という確固たるものがあるわけではなくて、他者と共に考えるからこそ、語ってしまうし問うてしまう。世界がわからないから、びっくりしてしまう。そうしたやり方でおそらくわたしたちは生きているはずなんです。だからこそ他者との対話が必要なのだと思います。
――哲学対話で、「ひとそれぞれはやめましょう」とお話しされている理由が気になりました。
そこはとても大切な部分だと信じています。ひとりで深く考えるときですら他者が必要なのに、「ひとそれぞれにしよう」というのはすごく寂しい言葉でもあると感じています。「あなたはあなたでご自由に」と。個人化が進むだけで、手が結ばれないですよね。写真家の友人、八木咲さんの書いた「バラバラなままで」という詩があるのですが、違うのはあたり前で、それぞれ異なる考えを持っているけれど、一緒のところもあるかもしれないと手を結び合う、話し合うということが哲学なのかなと。哲学的であることは対話的であることだと信じてやってきている気がしますね。(写真は永井さんと共に展示をした友人の写真家、八木咲さんによる詩「バラバラのままで」より)
――「対話」という言葉は「議論」とも異なります。「対話」とはなんなのでしょうか?
議論は他者を競争相手とみなしますが、世界はあまりにわからないことだらけなので、協力し合わないとどうにもならないと思うんです。ひとは誰しも生まれたけれどいつかは死ぬことになっていて、死んだ後はどうなるかも、なぜ生まれてきたのかもわからない。そうした共通するわからなさのなかに生きているからこそ、一緒に笑ってしまって、探求しようと協力し合えるはず。この「わたし」という確固たるものがあるわけではなくて、他者と共に考えるからこそ、語ってしまうし問うてしまう。世界がわからないから、びっくりしてしまう。そうしたやり方でおそらくわたしたちは生きているはずなんです。だからこそ他者との対話が必要なのだと思います。
――哲学対話で、「ひとそれぞれはやめましょう」とお話しされている理由が気になりました。
そこはとても大切な部分だと信じています。ひとりで深く考えるときですら他者が必要なのに、「ひとそれぞれにしよう」というのはすごく寂しい言葉でもあると感じています。「あなたはあなたでご自由に」と。個人化が進むだけで、手が結ばれないですよね。写真家の友人、八木咲さんの書いた「バラバラなままで」という詩があるのですが、違うのはあたり前で、それぞれ異なる考えを持っているけれど、一緒のところもあるかもしれないと手を結び合う、話し合うということが哲学なのかなと。哲学的であることは対話的であることだと信じてやってきている気がしますね。(写真は永井さんと共に展示をした友人の写真家、八木咲さんによる詩「バラバラのままで」より)
――永井さんは個人に向き合われながらも、社会や政治、環境などに対するはたらきかけもされていると思うのですが、それらはどのようにつながっているのでしょうか?
たとえば気候変動や環境問題などの大きな問題に対して、自分は関係ない、自分が意見を言っていいはずがないという感覚のひとはとても多いんですね。でもだからといって「自分ごとにしましょう」と言われても唐突すぎる。実はもっと手前のことが問われなくてはいけないと思っていて、その手前の部分をずっと耕している感覚があります。そもそも民主主義ってなに?とか、なんで地球規模のイシューをこのわたしが考えなくてはいけないの?とか。問いを立てること、わからなくなることって、一見すると後退しているように見えるんですけれど、問うことではじめてその言葉や世界と関係を持つことができる。問うことはみることなので。見ないと問えないんですよね。
――今お話を伺っているこの場所で、写真家の八木咲さんと「終わらせる」ための展示をしたのだと伺いました。一方で、哲学対話では「答えを出さない」で終わらせると伺いました。永井さんにとって「終わらせる」とはどんな意味があるのでしょうか?
わたしたちの生きているこの世界を見渡すと、木が植えられる一方で、伐採されたり建物が壊されたりということが劇的な早さで進んでいますよね。色々なものを大切に蓄積しながら、呆気なく壊せてしまうわたしたちでもあるわけです。写真家の八木咲さんはわたしの大切な友人なんですけれど、彼女にとって大切な場所で、わたしにとっても大切な築67年のこの建物もここに生えている木々も、あと少しで更地になって分譲マンションになると、突然終わりを告げられました。それで終わるに終われないのでこの家を弔おうという話になったんですけれど、終わりに向かっていく時間のなかで、「終わりってなんだっけ?」という問いが生まれて。「本当にここを終わらせなくてはいけないんだっけ?」と。哲学対話では、誰がどんなにいい話をしていて、どんなにわからなさの中にいても、時間がきたら終わらせるようにしているんです。もやもやしたままに帰ったら、きっと誰かに話したくなってしまうし、忘れられなくなりますよね。「終わらせる」ことで、哲学を「終わらせない」ようにできたらいいなと。ここに生えている木々も今いる建物も、目には見えなくなってしまうけれど、記憶という姿に形を変えて友人たちが持っていてくれることで終わらないかもしれないなと、今感じています。
わからなくなることって
一見すると後退している
けれど問うことで世界を
よくみることができる。
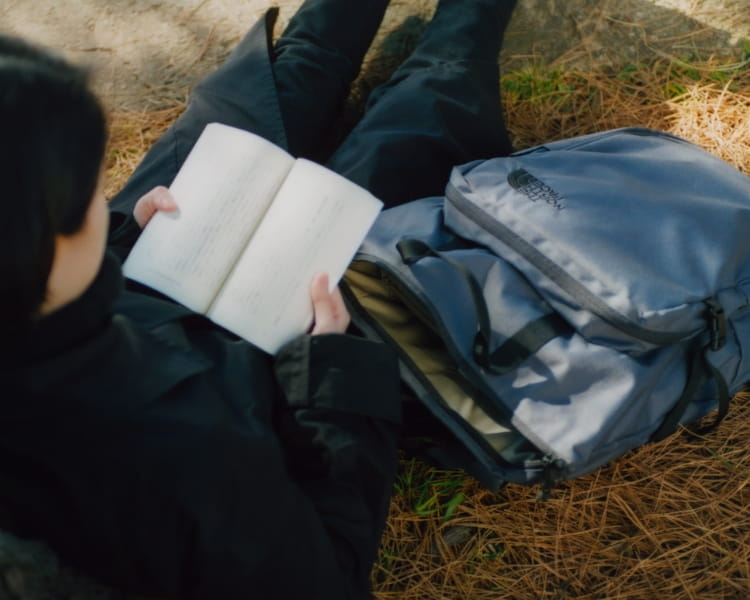



Rei Nagai
哲学者
学校・企業・寺社・美術館・自治体などで哲学対話を幅広く行っている。D2021メンバー。著書に『水中の哲学者たち』(晶文社)。連載に「世界の適切な保存」(群像)「ねそべるてつがく」
(OHTABOOKSTAND)「問いはかくれている」(青春と読書)「むずかしい対話」(東洋館出版)など。詩と植物園と念入りな散歩が好き。 国内外を問わず活動し、ギャラリーのキュレーターも務める。 主な個展に”Unusual Usual”(Portland, 2014)、 “Inside Out” (Warsaw, 2016)、”photosynthesis”(Tokyo, 2020)など。
Rei Nagai
哲学者
学校・企業・寺社・美術館・自治体などで哲学対話を幅広く行っている。D2021メンバー。著書に『水中の哲学者たち』(晶文社)。連載に「世界の適切な保存」(群像)「ねそべるてつがく」
(OHTABOOKSTAND)「問いはかくれている」(青春と読書)「むずかしい対話」(東洋館出版)など。詩と植物園と念入りな散歩が好き。 国内外を問わず活動し、ギャラリーのキュレーターも務める。 主な個展に”Unusual Usual”(Portland, 2014)、 “Inside Out” (Warsaw, 2016)、”photosynthesis”(Tokyo, 2020)など。

NM72251
ボルダートートパック
UNISEX
BUY
NM72251
ボルダートートパック
UNISEX
BUY